
「令和六年 第三回岐阜県議会定例会を終えて」
① 酒向薫の一般質問
1 中小企業・小規模事業者への支援について
(1) 賃上げに向けた取組みについて
答弁 商工労働部長
中小企業の賃上げ実現には、その原資の確保が最大の課題であると考えます。 そのため稼ぐ力の強化と適正な価格転嫁の両面から支援してまいります。 まず 「稼ぐ力の「強化」に向けては、 今年度、 事業転換や規模拡大に意欲的に取り組む小規模事業者への応援補助金を創設しました。 また、 ソフトピアジャパン、 テクノプラザものづくり支援センターによるDX 生産性向上支援のほか、新たに県試験研究機関の伴走のも
と、商品の試作から開発に至る技術の高度化や製造工程の自動化など、一貫した支援を実施してまいります。
次に 「価格転嫁」 の促進には、取引の川上から川下までの企業の機運醸成が重要です。 このため、県が呼びかけ、 3月に政労使23団体で締結した協定に基づきまして、価格転嫁への理解促進と団体間の連携を進めます。 具体的には、各業界の協定の実行音業状況を定期的に把握し、 好事例を共有するとともに、 価格転嫁の交渉に必要なデータなどを一元的に提供するホームページの充実を図ります。 これらの取組みにより、 価
格転嫁を促進し、適正な賃上げに繋げてまいります。
(2) 資金繰り支援の現状及び今後の取組みについて
答弁 商工労働部長
いわゆるゼロゼロ融資終了に伴う影響を抑えるべく、 令和5年1月に開始した有利な借換条件の「伴走支援型借換資金」 は、 直近の5月までに約2, 600件、 581億円の利用がございました。
議員ご紹介のとおり、 昨年の県内企業倒産件数はコロナ禍前の水準に抑えられています。 また、 本年4月が元金返済開始の最大かつ最後のピークでありましたが、 最新の状況としては、この1月から5月までの企業倒産件数は、前年同時期を4件下回る46件に留まっているところでございます。
これは、この資金が中小企業の資金繰りを支え、 倒産の回避や事業継続に一定の効果があったものと受け止めています。
その一方で国は、「コロナに焦点を当てた支援策は終了」 という方針を示し、 伴走支援型借換資金も取扱期限の到来を迎えます。 このため県では、 経営が苦しい事業者向け及び借換向け資金の償還期間を緩和した、つまり延長したメニューにより引き続き支援してまいります。 今後も県内中小企業の状況把握、 関係機関との情報共有を丁寧に行い、必要となる対策を検討してまいります。
2 食品ロス削減に対する県の現状認識と今後の取組みについて
答弁 環境生活部長
県食品ロス削減推進計画では、2030年度における食品ロス発生量を、国と同様に2000年度比で半減することを目標としております。 これまでに、 本県は約4割の削減となっておりますが、 国全体では半減目標を達成しており、本県では更に取組みを強化することが必要と考えます。
このため、食べ残しの削減に取組む 「ぎふ食べきり運動」 の協力店・企業を拡大するとともに、 商品棚の手前にある期限が近い食品を優先して選ぶ 「てまえどり」 などの実践的な取組みについて、 環境学習ポータルサイトやSNS等を活用して促してまいります。
また、 現在10の市町で実施されている、 各家庭の未利用食品をフードバンク団体などへ提供する「フードドライブ活動」 が全市町村で実施されるよう、働きかけてまいります。
なお、県民意識調査については、 令和3年度の計画策定時に実施しており、 計画の中間見直しに合わせ、 来年度実施してまいります。
3 農産物の価格に対する消費者の理解醸成について
答弁 農政部長
近年、国際情勢や為替の影響により、農業の生産資材は高騰しており、 例えば直近4月の肥料の価格は、令和2年と比較して1.34倍となっております。一方で、農産物の価格は1.12倍に留まっており、持続的な食料供給への影響が懸念されます。消費者には、こうした状況をご理解いただくことが重要であります。
このため、県内の直売所や量販店などで開催する地産地消フェアや、 県農業フェスティバルの機会を捉えて、 専用ブースを設けるなど、 主要品目における生産コストと価格の状況を、消費者に分かりやすく丁寧に伝えてまいります。
また、農業の生産コストや食の安全・安心をテーマに、 消費者との意見交換会を開催し、より効果的な理解醸成の方策について検討してまいります。
併せて、国に対しては、 合理的な価格形成の仕組みについて、 本県の生産現場の状況を反映するとともに、 消費者の理解を十分得られるものとなるよう、 働きかけてまいります。
②古田肇知事説明要旨
(能登半島地震における支援)
まず、能登半島地震における支援の状況についてです。本県では、県内すべての市町村や関係機関と連携した「オール岐阜」体制で支援に取り組んでまいりましたが、対口支援団体として指定された石川県中能登町では、すでに復興に向けたステージに入っており、輪島市でも、避難所の自主運営化などが順調に進んでいることから、先月末をもって、両市町への対口支援は終了いたしました。本県からの人的支援は、これまでに、県及び市町村合わせて、延べ約一万七千人・日に及んでおります。
今後は、公費解体や浄化槽復旧など個別に必要となる支援のほか、県及び市町村職員による中長期的な行政支援を実施してまいります。
(震災対策の見直し状況)
また、このたびの震災対応を踏まえ、本県の震災対策の見直しを進めております。四月には、庁内にプロジェクトチームを立ち上げ、「孤立やライフライン途絶の長期化への対策強化」、「建物耐震化の促進」、「避難所における生活・衛生環境の改善」、「災害対応における県・市町村間の連携強化」の四つのテーマを軸に、有識者を交え、課題の洗い出しや対策案の検討を行いました。被災地に派遣された職員や関係者が現地で得た知識や経験をも踏まえて、先般、「能登半島地震に学ぶ」と題し、中間報告として「今後の震災対策の方向性」をとりまとめたところであります。昨日開催した強靱化推進本部員会議では、来年一月の最終報告に向けて、さらに検討を深めていくことを確認いたしました。その上で、年度内には、「岐阜県強靱化計画」などの各種計画に反映し、県の防災体制に万全を期してまいります。
(Gクレジット制度の動向)
次に、GX(グリーン・トランスフォーメーション)の取組みについてです。昨年十一月から、本県独自の森林由来のカーボン・クレジットである、「Gクレジット制度」の運用を開始しております。先月十四日には、初となるGクレジットを認証し、早速、売買が成立したほか、多くの企業から購入希望の声があがっているところであります。また、Gクレジットの購入や普及啓発を通して、県の森林づくりを応援していただける企業などを「Gクレジットの森 応援パートナー」としておりますが、既に四百九十八者を登録しております。
(インバウンドの状況について)
次に、最近のインバウンドの状況についてです。令和五年の外国人延べ宿泊者数は、速報値ではありますが、令和元年以来、 四年ぶりに百万人を上回りました。また、先ほど議長もご挨拶の中でご紹介いただきましたが、月ごとの統計では、今年三月、初めてコロナ前を上回り、三月としては過去最高を記録するなど、着実に回復してきております。県内への「もう一泊」を促すプロモーションなどにより、今年度も引き続き本県の魅力を世界に発信し、更なる誘客につなげてまいります。
(木曽川中流域の観光振興など)
次に、木曽川中流域の観光振興についてです。今月十日、「木曽川中流域観光振興協議会」の総会を開催し、今年度の事業計画を決定いたしました。新たな試みとして、流域市町を巡るサイクリングイベントのほか、渡し船をコース内に組み込んだガストロノミー・ウォーキングを実施いたします。加えて、来月には、ドイツのライン川流域の観光事業及びクアオルト(温泉などを活用した療養地) 事業を視察し、これらの先進的な取組みを参考に、更なる事業の展開につなげていくことといたしました。
(「岐阜県経済・雇用再生会議」の開催)
次に、先月二十七日に開催しました。「岐阜県経済・雇用再生会議」についてです。県内の経済団体、金融機関、観光業、農林業、建設業などの代表者や、岐阜労働局などの国の機関にもご参加いただき、ご意見をいただきました。賃上げについて、非製造業の伸びが鈍く、業種間に開きがあることや、小規模事業者では、十分進んでいないといった報告がありました。また、下請け企業は、発注企業との関係から、価格転嫁が難しいといった切実な声も聞かれました。売り上げを伸ばし、このほか、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進することにより、若者が活躍する好事例があることなどのご意見もありました。引き続き、物価と賃金の好循環に向け、県として必要な対策を推進、検討してまいります。
(「ぎふ若者定着奨学金返還支援制度」の募集開始)
次に、若者の県内の就職促進に向けた取組みについてです。県では、若者の県外流出、企業の人材不足という課題を踏まえ、県内企業に一定期間就業された方の奨学金の返還を支援する、「ぎふ若者定着奨学金返還支援制度」を今月からスタートいたしました。既に、十五の企業から本制度利用の応募をいただいております。
(「岐阜県日本語学習支援センター」の開設)
次に、「岐阜県日本語学習支援センター」の開設についてです。昨年末時点で、本県における外国人県民は過去最高の六万九千人にのぼり、今後も、更なる増加が見込まれております。こうした状況を踏まえ、本日、県国際交流センター内に、「岐阜県日本語学習支援センター」を開設いたします。このセンターでは、日本語教育を担う人材の育成や、市町村や企業などが設置する日本語教室への支援などをワンストップで行い、日本語学習支援の中心的役割を果たしてまいります。
(国民文化祭などの開催に向けた動き)
次に、国民文化祭などの開催に向けた取組みについてです。まず、「清流の国ぎふ総文2024(にせんにじゅうよん)」については、先月三十日に開催した実行委員会において、高校生がこれまでの取組みや今後の活動を報告したところでありますが、(来月末の開催に向け、着実に準備を進めてまいります。続いて、開催まで四か月を切った「『清流の国ぎふ』文化祭2024(にせんにじゅうよん)」については、「清流文化地域推し活動」、愛称「ちーオシ」を実施してまいります。このため各市町村の「いち推し」を表現した「ちーオシスタチュー」を制作することとし、すでに二十六市町村において着手しております。このほか、今月七日から、岐阜の文化に関する写真や動画をSNSを通じて発信いただく#はっしゅたぐ)わたしの清流文化プロジェクト」の投稿拡大キャンペーンを展開しております。
(万博国際交流プログラムの選定)
最後に、国際交流に係る取組みについてです。国では、来年の大阪・関西万博を契機に、地域住民と参加国の関係者が継続的な国際交流を行う「万博国際交流プログラム」を進めております。本県からは、開催地である大阪府に並ぶ、全国最多の八カ国との交流プログラムが登録されております。これに加えて、県内三市町もそれぞれ独自のプログラムを登録しております。今年は、「世界に開かれた文化の大交流」として、国民文化祭にも海外から多くの方々に参加をいただく予定であります。こうしたグローバルな文化交流を通じて、本県の魅力の再発見や新たな清流文化の創出につなげてまいります。

【6月29日】
「板取あじさい村フェスティバル2024」
(長屋晃寛実行委員長) 関市板取21世紀の森公園
旧板取村から37回目の伝統ある祭りです。5万本のあじさいが自然に恵まれた風光明媚な板取は宝の宝庫です。
天候不順のなか、5万本のあじさいの管理は大変です。関係者の皆さんに感謝です🙇。
板取小学校6年生の4人の村長が立派な挨拶をしました。

【6月28日】
第139回 関商工会議所 通常議員総会 (鈴木良春会頭)
約1900人の従業員が会員です。
渡辺猛之参議院議員も出席されました。

【6月25日】
第27回JRP岐阜写真展 〜わたしの視線〜 岐阜県美術館
すぐれた日本文化の伝統と写真の歴史的成果をリアルに表現された写真ばかりで素晴らしいです。
関市武芸川町堀野慎吉先生の作品も展示してあります! 是非ご覧ください。

【6月24日】
令和6年度第3回 岐阜県議会定例会 一般質問に登壇!!
6月26日4番目 午後3時前後
質問内容は次の通りです。一生懸命頑張りますから応援宜しくお願い致します。

【6月24日】
中部学院大学 「現代マネジメント研究」
テーマ 『こころをつなぐ音楽療法』
講 師 ヴァイオリニスト・岐阜県音楽療法士 『濱島 秀行氏』

【6月23日】
返還30年 岐阜の赤羽刀総覧 岐阜県博物館
室町時代から江戸時代末までの赤羽刀70振が展示されています。関係者は勿論、私のような素人でも目から鱗になりました。

【6月23日】
第21回 『関日本画協会展』 関市文化会館
「秋季」 平野 義文作
「春遠望」 森 通作
いずれも150号の大作、7名32作品を拝見しました。
正にプロ中のプロに感動しました。

【6月23日】
『夏のやさい祭り』 中濃公設卸売市場
インターネットを通じて農業の楽しさを伝える人気ユーチューバーがトークショーを繰り広げられ、関市「たわらファーム代表で農業系ユーチューバーの川村雄祐さんが司会進行を務めた。
いろいろな農産物やキッチンカーで会場は沢山の人で賑わいました。
農業資材など、物価高騰が農家を直撃しています。食料の依存は輸入が高く重大な課題です。
消費者も価格転嫁について理解して頂く時だと思います。

【6月22日】
中濃体育協会情報交流会(土本恭正会長) 美濃 緑風荘
関市、美濃市、郡上市の各市長、各スポーツ協会長そして各競技団体が一堂に集まり話し合いました。

【6月21日】
JAめぐみの 第21回通常総代会 (山内清久組合長) 関市文化会館
正准組合員 61,032人
総代 990人

【6月20日】
関市学校規模適正化計画説明会 富野地区 富野小学校体育館
関市教育委員会が関市各地で計画説明会を開催しています。
この富野小学校中学校は旭ヶ丘小学校中学校との統廃合の計画がある旨の説明会となり、富野地区住民約120名が出席され存在要望の意見が活発に出され2時間に及ぶものとなりました。
富野地区住民の結束と郷土愛そして、子供へのひとしおでない愛情を改めて素晴らしいと感じました。
まだまだ、決論は出ていませんが、関市教育委員会も住民意見を踏まえて慎重に丁寧に進める必要が有ります。

【6月20日】
毛筆かな教室 作品発表会 せきまちかどギャラリー
主宰 佐藤芳舟さん
30人の生徒さんが百人一首や漢字をモデルに力作を披露しました。
大河ドラマ「光る君へ」の源氏物語からの作品も有ります。是非ご覧下さい。

【6月17日】
中部学院大学 「現代マネジメント研究」
テーマ 『不易流行のおもてなし』
講 師 株式会社十八楼取締役・長良川温泉女将会会長 伊藤 知子氏

【6月16日】
墨扇会書道会 せきまちギャラリー 塚原秋扇主宰
書道教室12人の力作でそれぞれ個性のある作品ばかりです。

【6月16日】
第2回河上薬品グループ杯争奪大会開会式 河上薬品スタジアム
12チームが優勝目指し戦います。
河上薬品グループ河上宗勝代表取締役社長の始球式で開幕しました。

【6月15日】
岐阜県立関高等学校 同窓会総会 美濃観光ホテル
関高校第32回第33回卒業生合同懇談会も開催され、112名が参加してお互いの親睦を深めました。武田理関高校長も出席され、関高校の現状についてお話されました。
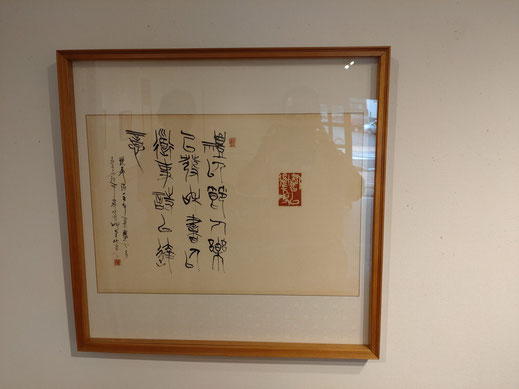
【6月9日】
2024 関中印社篆刻展 関まちかどギャラリー
平田蘭石門下の皆さんがそれぞれの素晴らしい作品を披露しました。是非ご覧下さい。

【6月9日】
関山草会・蘭峰書道会 関市若草ブラザ
各会のメンバーが日頃の作品を一堂に披露しました。
是非、ご覧下さい。

【6月4日】
令和6年度 関市シルバー人材センター定時総会 (岡田 誠理事長)
令和5年度決算 会員数754人
受託事業3億8500万円(内派遣事業2億1500万円県下1位)
生産年齢人口の人手不足をシルバー人材が関市の産業を支えています。
長年、功績があった企業個人の皆さんが表彰を受けられます。

【6月3日】
2024年度 中部学院大学 『現代マネジメント研究』
テーマ 「我が国のがん対策について」
講師 岐阜県健康福祉部長 丹藤 昌治氏
医師の数と種類
医院医師約312,000人
研究医師約5,200人
医療技官約2,100人
(内訳)行政医師約1,800人
厚生労働省医師約300人
国の社会保障関係72.7兆円の内医療費が51%の36.9兆円を占める。
がん患者は約170万人、その医療費は約12%の3.8兆円になる。

【6月2日】
第66回 関市消防安全競技大会 中濃公設地方卸売市場
操法の部 倉知分団、安桜分団
競練の部 富岡分団他15分団

【6月1日】
セキ日和 関市本町 商店街空き店舗マルシェ盛況
30ヶ所に飲食物品100
地元関市のお店にも沢山のお客で活気。
関市本町商店街に毎日行こう。

【5月30日】
関市「人・農地プランから地域計画へ」 富岡ふれあいセンター
(地域農業の将来の在り方)から(令和7年を目処に農業経営基盤強化)へ
現在の僅々の課題、農業者の減少や耕作放棄地の拡大など地元の住民皆んなで考えて行きます。
「地域の課題は地域皆んなで考えよう!明日の地元の反映のために!」
次回は地元の農業者の皆さんにも沢山参加して頂きます。
ちなみに、私は阪口慶三先生の学校の硬式野球部の後輩です。

【5月30日】
第48回全国高等学校総合文化祭 第3回岐阜県実行委員会
岐阜県庁 「清流の国ぎふ総文2024」
7月31日から8月5日
テーマ 『集え青き春 湧き出せ知の筏 水面煌めく清流の国へ』
全国、韓国、ベトナムやリトアニアなど高校生2万人が参加します。
関市からは全国大会グランプリ賞を獲得した『関商工写真部』写真を発表します。
皆さん、岐阜県の将来を担う高校生のイベントを是非ご覧下さい。
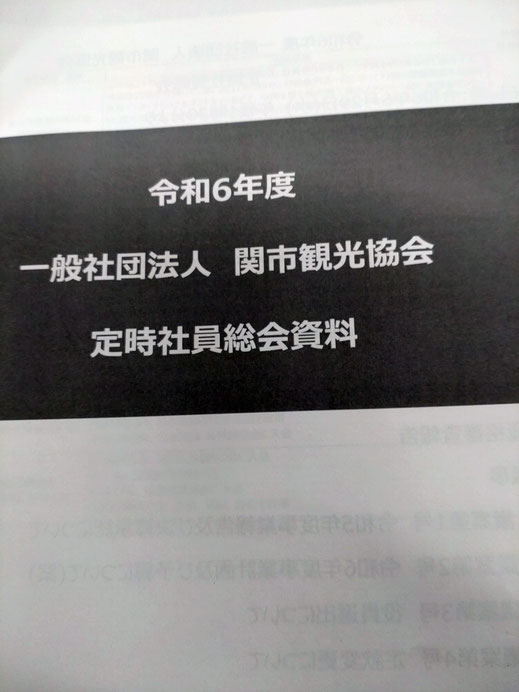
【5月29日】
令和6年度 関市観光協会総会 せきテラス
関市観光協会表彰があり、次の5名の皆さんが表彰されました。
酒井雅俊、長谷部和子、各務弦太各氏他です。

【5月28日】
令和6年度 関市土木行政岐阜県要望会議 関市役所
関市から道路建設、河川改修、砂防事業等48事業(重点12事業)の早期着工要望がありました。関市民の生命財産を災害から守る強靱化対策やインフラ、産業振興など重要な事業ばかりですから、早期着工に勤めます。
コメントをお書きください